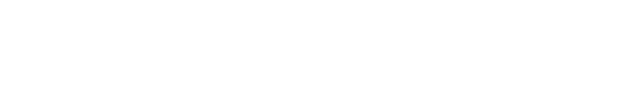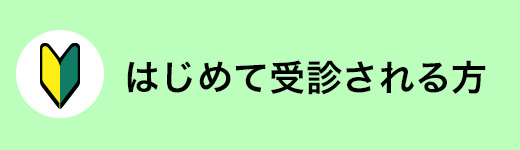免疫機能・免疫異常
「今まで風邪なんてほとんど引かなかったのに、今年はよく引くようになった」「風邪を引くとなかなか治らなくなった。昔はこんなことなかった」「最近よく熱を出すようになった」
このように感じたことのある方は少なくないと思います。
体調不良が続くと、何か病気があるのではないか、免疫に異常があるのではないか、と心配になる方もいらっしゃいます。
免疫機能、免疫異常について、できるだけわかりやすくご説明したいと思います。免疫は本来非常に緻密で専門的で難解な領域のため、全てをご説明できないことをご容赦ください。また、免疫異常のうち自己免疫はアレルギー・膠原病科の専門となるため、ここでは免疫機能の低下に限らせていただきます。
免疫とは
免疫機能と聞くと、白血球をはじめとする免疫細胞がイメージしやすいかもしれません。白血球の中にも機能が様々な複数の種類があり、また、広い意味では免疫細胞だけでなく、普段は意識しない体の構造によるバリアも大変重要です。
例えば、口や鼻・消化管の粘膜、唾液、気管・消化管の粘液、全身の皮膚は、病原体や異物がそもそも体内に侵入しないよう機能しています。ひいてはくしゃみや咳といった症状も、実はバリア機能を担う反射運動です。
これらを突破して侵入してきた病原体や異物に対し、機能するのが白血球です。白血球には複数の種類がありますが、そのうち主に働くのは次の細胞たちです。
◎免疫細胞
| 好中球 |
マクロファージに呼ばれて病原体の侵入に動員され、飲み込んで消化する。その後は死んでしまう。細菌、真菌に働き、ウイルスには作用を持たない。 |
|
単球 マクロファージ |
侵入した病原体をその場で真っ先に飲み込んで消化する。血液中では単球、組織の中に移動するとマクロファージになる。マクロファージは免疫反応を促すための機能を多彩に持っている。細菌、真菌の他、腫瘍細胞にも作用する。 |
|
Bリンパ球 形質細胞 |
抗体(免疫グロブリン)を作る。抗体は細菌や真菌にくっつき、かつ免疫細胞とも結合し、病原体と免疫細胞との橋渡しをすることで、免疫細胞による駆除作用を活性化させる。Bリンパ球が機能的に少し変化すると形質細胞になる。 |
| Tリンパ球 | ウイルスに感染した細胞に結合したり、免疫反応をコントロールすることで、ウイルス感染細胞を駆除する。 |
| NK細胞 | 生まれた時から備わっている細胞。ウイルスに感染した細胞や、がん細胞を駆除する。 |
病原体や異物に対する免疫反応は、ワンパターンではなく非常に複雑で多彩ですが、大きく分けると次の3パターンに分かれます。
◎免疫反応
1) 好中球、マクロファージによる貪食(どんしょく)作用
病原体が侵入したその場で真っ先に起こる免疫反応。マクロファージ、好中球が飲み込んで、細胞内で消化する(貪食する)。細菌、真菌に有効だが、ウイルスには無効。好中球が大量に死ぬと膿ができる。
2) Tリンパ球などによる細胞性免疫
病原体が免疫細胞の中に取り込まれると、取り込んだ免疫細胞を感知して免疫反応が作動、免疫細胞ごと駆除する。ウイルス、細菌に対し有効。Tリンパ球、単球/マクロファージ、NK細胞が関わっており、リンパ組織で行われる。
3) Bリンパ球などによる液性免疫
病原体を抗体(免疫グロブリン)で駆除する。抗体はBリンパ球、形質細胞によって作られ、新しい病原体と遭遇するたびにそれに見合った抗体をどんどん作り出していく。抗体が病原体にくっつくことでマクロファージが病原体に気づきやすくなり、駆除を促す。病原体や毒素を取り囲んでリンパ球への侵入を防いだり、毒素を中和したりもする。細菌、真菌に有効。
免疫の場所
- リンパ節;全身を巡る血液に由来するリンパ液は、リンパ管と呼ばれる管を通って全身を巡る。このリンパ管が全身のところどころで形成している器官で、大きさは2mm〜1cm程度、数は500程度。
- 脾臓;左脇腹に位置する10〜12cmほどの臓器。大量の病原体や異物が活発な免疫作用により駆除されている。
- 小腸粘膜
病原体にも種類がある
病原体には、風邪の原因となるウイルスの他に、細菌(結核菌を含む)、真菌、原虫など複数の種類があります。白血球の種類によって、駆除対象となる病原体は違いがあります。どの白血球に異常があるかで注意すべき感染症の種類も異なります。
一般的に細菌には抗生物質が有効ですが、ウイルスには無効です。抗生物質にも複数の種類があり、菌によって有効な抗生物質はいくらか異なります。ウイルスは一部のウイルスを除き、治療薬がありません。風邪を治す薬はないというのは、風邪を起こす原因ウイルス(ライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルス、アデノウイルスなど多数)に有効な薬がないためです。ウイルスの多くは、体の持つ免疫機能で駆除するしかありません。インフルエンザウイルス、ヘルペスウイルス(単純ヘルペスウイルス、水痘帯状疱疹ウイルス)、サイトメガロウイルス、HIVなどには治療薬があります。
免疫異常の原因、症状
免疫細胞に異常をきたし、多彩な免疫反応のいずれかに障害をきたしたものが免疫異常です。先ほどの3パターンの免疫反応が、どのような原因で障害され、また障害された場合はどのような病原体に注意が必要かをお示しします。
[1]好中球の異常
| 異常となる原因 | 主に注意するべき病原体 |
|
抗がん剤、ステロイド 原発性免疫不全症候群 |
細菌(ブドウ球菌、肺炎球菌、大腸菌などの細胞外寄生菌) 真菌(カンジダ、アスペルギルスなど) |
[2]細胞性免疫の異常
| 異常となる原因 | 主に注意するべき病原体 |
|
ステロイド、免疫抑制剤 抗がん剤(シクロフォスファミド、プリンアナログ)、抗体製剤 抗胸腺グロブリン、造血幹細胞移植後 リンパ腫、HIV感染症 栄養不良、高齢 原発性免疫不全症候群 |
ウイルス(単純ヘルペスウイルス、サイトメガロウイルスなど) 細菌(結核菌、レジオネラなどの細胞内寄生菌) 真菌(カンジダ、アスペルギルス、ニューモシスチス、クリプトコッカスなど) 原虫(トキスプラズマなど) *注意するべき病原体が広範囲にわたります |
[3]液性免疫の異常
| 異常となる原因 | 主に注意するべき病原体 |
|
B細胞性リンパ腫、多発性骨髄腫、鎌状赤血球症 抗体製剤、脾臓摘出 原発性免疫不全症候群 |
一部の細菌(肺炎球菌、インフルエンザ菌、髄膜炎菌など) ウイルス(コクサッキーウイルス、日本脳炎ウイルスなど) |
免疫異常は、病院などの医療機関で受けた治療が原因となることがあります。何らかの病気があって、ステロイドや免疫抑制剤の投薬を続けている、抗がん剤治療をしている、放射線治療をしている、手術で脾臓をとった、移植治療を受けた、などで免疫機能低下をきたします。血液疾患(白血病、リンパ腫)は白血球の腫瘍ですので、病気自体が免疫機能に影響を及ぼします。その他、原発性免疫不全症候群という病気があります。
原発性免疫不全症候群は基本的に遺伝性のため、小児期に感染症を繰り返すことがきっかけで診断されます。まれに成人になってから診断されることもあります。多くの分類があり、好中球やマクロファージの異常なのか、細胞性免疫の障害なのか、液性免疫の障害なのか、専門家のもとで精密検査を行います。
その他身近に多いところでは、糖尿病もコントロールが悪い場合は免疫機能に影響します。腎機能や肝機能の高度な低下も免疫機能低下をきたします。
免疫機能の評価においては、このような原因や、体のバリア機能の異常、臓器機能に影響する他の病気がないかの確認を行うことが大切です。血液検査としては、白血球・白血球分画や免疫グロブリンの測定を行います。どちらも当院では検査可能です。
これらに異常がなければ、風邪にかかりやすい、治りにくいというのは、生活の変化(忙しい、疲れがたまっている)に伴う一時的な体調変動と思われ、病的とは思われません。疲労で免疫機能の効率が一時的に落ちてしまうことは、誰しも起こりうることであり、病気というわけではありません。
免疫異常の治療
健常者よりも感染症にかかりやすくなるため、ワクチンや予防投薬(抗生物質、免疫グロブリン製剤)による感染予防と、感染症にかかった時の早期治療が中心となります。上述の通り、どの種類の免疫機能が障害されているかにより、注意するべき病原体が異なります。ワクチン接種による効果およびワクチン自体による感染リスク(生ワクチンの場合)の観点から、患者さんごとに勧められるワクチンの種類や接種の時期は異なります。
例)
- 脾臓摘出:手術前に肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチン、髄膜炎菌ワクチンが強く勧められます。
- 造血幹細胞移植後:移植後のワクチンをご参照ください
免疫グロブリン製剤は、液性免疫に関連する抗体(抗体5種類のうちのIgG抗体)を製剤化したものです。免疫異常を有する方が感染症になった場合、必要に応じて抗生物質などの治療と併行して投与されます。原発性免疫不全症候群や、血液疾患、治療などで液性免疫が高度に低下している方においては、感染予防のために投与されることもあります。
まとめ
免疫機能=体には皮膚や粘膜などのバリア機能が備わっており、バリアの先には各種免疫細胞が役割分担をしながら病原体を絶えず駆除している。免疫機能が正常でも、疲労などで一時的に要領が悪くなってしまうことはある。
免疫機能に異常をきたす原因=医学的治療、血液疾患、原発性免疫不全症候群、糖尿病、内臓疾患(腎不全、肝不全)