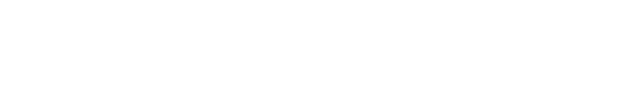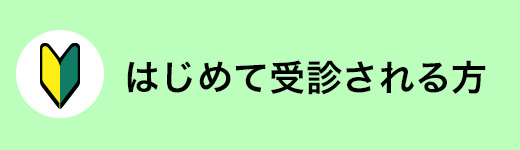真性多血症
真性多血症はどんな病気?
赤血球を造る骨髄で、造血の大元となる細胞に遺伝子異常が発生し、赤血球産生が必要以上に加速されて過剰となってしまう病気です。特に症状はなく自覚されないことが多く、健診などで血液検査を受けたときに、赤血球関連の数値(ヘモグロビン、ヘマトクリット、赤血球数)が高いと指摘され、見つかることが多いです。まれにだるさ、皮膚のかゆみ、お腹の張りや不快感(脾腫=脾臓が大きくなることによる)、体重減少を伴うこともあります。
診断
多血症があり、エリスロポエチンの数値が低い場合に疑われます。
真性多血症ではほとんどの方でJAK2V617F変異と呼ばれる遺伝子変異が見られます。95%の方で陽性と言われ、保険診療で血液検査で調べることができるため、やや高額(3割負担の方で7500円程度)ではありますが、真性多血症の可能性を評価するために勧められる検査です。JAK2V617F変異が陽性であれば、真性多血症の可能性が極めて高くなりますが、最終的には骨髄検査を行い、血液細胞の全体的な増加所見などを確認し診断確定となります。
治療
- 血栓予防
血栓症を予防することが主な治療目的となります。このため、血液をサラサラにする薬(アスピリン)の内服が勧められます。理想的な目標値はヘマトクリット値45%以下であり、瀉血という方法も用いられます。瀉血は、献血のようなイメージで、血管に点滴針を挿入・留置し、空のバッグに1回200〜400ml程度の血液を流出させ、体内の血液を少しずつ少なくする治療です。
- 赤血球産生を抑える薬
血栓症のリスクは年齢に伴い高くなってしまいます。年齢61歳以上の方、過去に血栓症の既往がある方は、過剰な赤血球産生を抑えるヒドロキシウレア(ハイドレア)という内服薬が勧められます。ヒドロキシウレアは抗悪性腫瘍剤に分類されるお薬ですが、通常は自覚する副作用はほとんどなく、継続可能です。
※ヒドロキシウレアの他にルキソリチニブといった治療薬もありますが、ヒドロキシウレアの方が使いやすいお薬であるため、通常はヒドロキシウレアが用いられます。
- 新しい治療薬
これらの治療薬でヘマトクリット値の低下が不十分な場合、また、ご妊娠でヒドロキシウレアが使用できない場合は、インターフェロンの皮下注射による治療も可能です。インターフェロン(正式名称:ロペグインターフェロンα2b、商品名:ベスレミ)は、2週に1回の皮下注射のお薬です。注射方法を覚えれば、ご自身による注射も可能です。投与により発熱、倦怠感、食欲低下、白血球や血小板の減少といった副作用が出ることがあります。この病気の原因となる根源的な細胞を抑える効果が期待されていますが、2023年に販売開始となった新しいお薬であるため、長期的な治療成績に関するデータはまだ不十分です。高額薬剤のため一般的に高額療養費制度が利用されています。
- 治療以外に大切なこと
治療法としては上記の通りになりますが、血栓症には高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙、肥満など複数の発生要因があります。これらの持病や因子がある場合は、できるだけ改善を目指し血栓リスクを軽減させることも重要となります。
長期経過について
腫瘍性疾患の一種ですが、予後は比較的良好です。長期経過で、時に骨髄が線維化と呼ばれる変性をきたしたり、白血病に移行したりすることがあります。
血栓症予防を第1目標に長期管理が重要です。