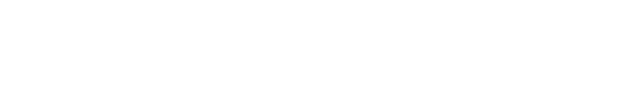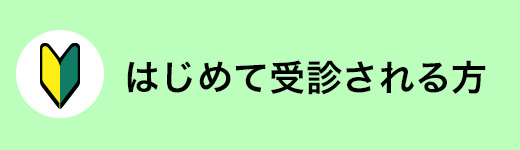慢性リンパ性白血病
慢性リンパ性白血病とは
通常無症状のため、健診などでたまたま血液検査を受けた際に白血球増加を指摘され、診断されることが多いです。白血球の内訳を見ると、リンパ球の割合が上昇しています。日本人における罹患率は10万分の1未満と非常に稀で、欧米に多い病気です。
リンパ球(B細胞性)が腫瘍化し、慢性的に増加しています(リンパ球数は通常多くても4800/ul以下ですが、5000/ul以上となります)。主に骨髄〜血液で増加しますが、リンパ球の居場所であるリンパ節や脾臓、肝臓で増加し、リンパ節腫脹や脾腫(脾臓が大きくなる)、肝腫大(肝臓が大きくなる)をきたすこともあります。
診断
血液中のリンパ球数が5000 /μl以上のとき、骨髄検査を行い、慢性リンパ性白血病の特徴と一致するリンパ球の増殖が確認されると診断となります。
全身のCT検査を行い、リンパ節腫脹や脾腫、肝腫大の有無を確認します
病期(ステージ)
病期分類は2つあります。
Rai(ライ)分類(0期が初期、Ⅲ〜Ⅳ期が進行期)
| リスク | ステージ | |
| 低リスク | 0期 | |
| 中間リスク | Ⅰ期 | 0期+リンパ節腫脹あり |
| Ⅱ期 | 0〜Ⅰ期+(脾腫 ± 肝腫大) | |
| 高リスク | Ⅲ期 | 0〜Ⅱ期+貧血(ヘモグロビン<11) |
| Ⅳ期 | 0〜Ⅲ期+血小板減少(<10万) |
Binet(ビネ)分類(A期が初期、C期が進行期)
| ステージ | |
| A期 | [リンパ節腫脹(頸部、腋窩、鼠径)、脾腫、肝腫大が2ヶ所以下]かつ、ヘモグロビン10以上かつ、血小板10万以上 |
| B期 | [リンパ節腫脹(頸部、腋窩、鼠径)、脾腫、肝腫大が3ヶ所以上]かつ、ヘモグロビン10以上かつ、血小板10万以上 |
| C期 | ヘモグロビン10未満 ± 血小板10万未満 |
治療
治療をしても完治はしないため、治療の必要性は待機的に検討されます。病気が見つかっても、その時点で症状はなく体の影響もない方が多いです。白血球の数が3万、5万を超えることも珍しくはありませんが、リンパ球が多いだけでは治療はしません。次のいずれか1つ以上当てはまるものがあるときは、治療を検討します。該当しないときは、定期的な診察、血液検査で病状観察を続けていきます。
| 貧血の進行(ヘモグロビン <10) |
| 血小板減少(<10万) |
| 10cm以上のリンパ節腫脹 |
| 高度な脾腫 |
| リンパ球の急な増加傾向(2ヶ月で1.5倍以上) |
| 症状(発熱、強い寝汗、倦怠感、体重減少) |
| 病気に関連した自己免疫性の貧血や血小板減少の進行 |
治療は過去は抗がん剤治療が主体でしたが、近年はより有効性の高い内服薬が使えるようになりました。初回治療ではブルトンキナーゼ阻害薬の内服が標準的です。
| 薬剤(一般名) | 薬剤(商品名) | 備考 | ||
| イブルチニブ | イムブルビカ | ブルトンキナーゼ阻害薬 | 内服 | |
| アカラブルチニブ | カルケンス | |||
| ザヌブルチニブ | ブルキンザ | |||
| ベネトクラクス | ベネクレクスタ | BCL2阻害薬 | 内服 | 再発時、初回治療無効の場合に保険適応 |
| オビヌツムマブ | ガザイバ | CD20モノクローナル抗体 | 点滴 | |
| リツキシマブ | リツキサン | |||
| ベンダムスチン | トレアキシン | 抗がん剤 | 点滴 |
注意点
・リンパ球の異常により体内のリンパ系免疫異常を併発し、自己免疫性の血小板減少症(ITP)や溶血性貧血(AIHA)を合併することがあります。この場合、まずはITP、AIHAに準じた治療を試みます。
・まれに悪性度の高いリンパ腫や白血病に移行することがあります。(未治療例では年間0.5%、治療例では年間1%程度)